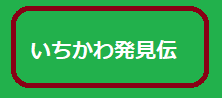メンバーの根岸英之さん(市川民話の会)は、市川緑の市民フォーラムの会報『みどりのふぉーらむ』に「文芸からみる市川の自然」という連載を執筆しています。
市川は文化と自然が豊かなまち。その双方の視点から市川を再発見する情報が満載です。
当サイトで、連載のアーカイブ化を図っていきます。
文芸からみる市川の自然 2024年
105 牧野富太郎の市川での採集標本の意義 (194号 2024年2月)
106 ムジナモは市川でも棲息していた (195号 2024年4月)
107 じゅん菜池のオオミクリとヒメミクリ (196号 2024年6月)
108 里見公園下にあった栗市の渡しと大正2年の湯島小学校遠足事故(197号 2024年8月)
109 大正2年の湯島小学校遠足事故から民話「三人地蔵」へ (198号 2024年10月)
110 中国分・じゅん菜池の「姫宮」とヘビ (199号 2024年12月)
「市川に通い続けた牧野富太郎-〈市川学〉へのいざないー」根岸英之
「ひと模様 根岸英之さん」
「食べ物と戦争話 千葉県市川市の「兵隊の西瓜泥棒」」根岸英之
🔊 2024年5月11日「じゅん菜池を考える会」
「じゅん菜池に通い続けた牧野富太郎ー〈市川学〉へのいざないー」根岸英之
🔊2024年6月22日「2024年度 文化財保存全国協議会第54回市川大会 懇親会」
「市川における牧野富太郎の標本採集ー市街化の中での〈遺産〉の継承ー」根岸英之
「井上ひさしと国分ー『ドン松五郎の生活』を中心にー」根岸英之
「国府台・真間に住みつく”まちわらし”とは いちかわ市民ミュージカル 9月に公演」
「井上ひさしと国分ー『偽原始人』を中心にー」根岸英之
「市川民話の会の取り組みから」根岸英之
🔊2025年1月18日「じゅん菜池を考える会」
「井上ひさしと国分」第3弾ーエッセイを中心にー 根岸英之
103号、104号に続き、植物分類学者の牧野富太郎と市川の関わりについて調べた内容で、市川で採集された標本には、新発見の標本なども含まれることを紹介しました。標本画像は東京大学植物標本室所蔵。
http://www.biol.se.tmu.ac.jp/herbarium/
https://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DShokubu/herbarium/en_ver2/index.php?-langTop=
🔊国立科学博物館タイプ標本データベース
https://type.kahaku.go.jp/TypeDB/search?cls=vascular
103号、104号、105号に続き、植物分類学者の牧野富太郎と市川の関わりについて調べた内容で、富太郎が市川の対岸小岩でムジナモを発見した日は市川も訪れていたこと、市川でも富太郎以外の研究者によって3か月後にムジナモの標本採集が行われていたことなどを紹介しました。標本画像は東京大学植物標本室所蔵。
https://www.aozora.gr.jp/cards/001266/files/47239_29289.html
🔊『千葉県レッドデータブックー植物・菌類編』(2023年改訂版)「ムジナモ」p102
🔊「東京大学総合研究博物館ニュース」Volume13/Number1「常設展 時を越える自然の証人 -東京大学収蔵・植物標本-」
https://www.um.u-tokyo.ac.jp/web_museum/ouroboros/v13n1/v13n1_ikeda.html
103号から続く、植物分類学者の牧野富太郎と市川の関わりについて調査した内容で、1893(明治26)年9月、富太郎が中国分のじゅん菜池(富太郎は国府台じゅん菜沼と呼んでいた)を(確認できる範囲で)初めて訪れ、水辺に生える多年草のオオミクリ(当初はアヅマミクリと呼称)とヒメミクリを標本採集し、その標本が基準となって、オオミクリとヒメミクリが、新種として認定されたことに言及しました。標本画像は東京大学植物標本室所蔵。
🔊https://www.facebook.com/share/qwAg6PxyH3Gh36fn/
1913(大正2)年5月6日、現在の里見公園下の河川敷の休憩トイレの辺りにあった「栗市の渡し」で、国府台へ遠足に来た東京の湯島尋常小学校の児童の乗った船が転覆し、3名の児童が亡くなるという事故が起きました。その顛末を採り上げました。
いちかわ市民ミュージカルに描かれる市川の見どころを歩く~栗市(くりいち)の渡しと三人地蔵編
「国府台・真間に住みつく”まちわらし”とは いちかわ市民ミュージカル 9月に公演」
1913(大正2)年5月6日、「栗市の渡し」で、東京の湯島尋常小学校の児童の乗った船が転覆し、3名の児童が亡くなるという事故が起きました。児童を供養するため「三人地蔵」が建立された経緯や、出来事が「話」として語り継がれていく様子を紹介しました。
来年の干支・巳年にちなんで、中国分・じゅん菜池の「姫宮」に伝わっている、ヘビにまつわる伝承を紹介しました。国府台合戦の「姫入水」伝承が広く知られていますが、ヘビの登場する伝承は、より民俗的な色彩の強く残るものといえるでしょう。
2024年3月17日「千葉日報」
「ひと模様 ”文化の街”魅力探して 歴史や民話発信、「市川学」提唱 根岸英之さん」
2024年3月20日「日本民話の会通信」No.269
「食べ物と戦争話 千葉県市川市の「兵隊の西瓜泥棒」」根岸英之
2024年5月11日「じゅん菜池を考える会」
「じゅん菜池に通い続けた牧野富太郎ー〈市川学〉へのいざないー」根岸英之
講師・根岸英之さんが、明治時代から戦前までじゅん菜池で植物採集した牧野富太郎を語ります。
根岸講師がこつこつと調べ上げたと実感させられる素晴らしい研究調査結果です。
会場は、5月11日(土)に市川市中国分にある西部公民館。お時間ありましたらご参加下さい。
自然豊かだった市川を見直しましょう!
2024年6月22日「2024年度 文化財保存全国協議会第54回市川大会 懇親会」
「市川における牧野富太郎の標本採集ー市街化の中での〈遺産〉の継承ー」根岸英之
富太郎が、明治17(1884)年から毎年または数年おきに市川の主に、国府台、市川、真間を訪れ、標本採集したあらましを、各植物園に所蔵されている標本データから明らかにし、小岩で発見した「ムジナモ」は市川でも棲息していたこと、「オオミクリ」と「ヒメミクリ」はじゅん菜池での採集標本によって種として認定されたこと、などを紹介し、それは市川における考古学調査研究の学史と重なっていること、富太郎の市川での足跡や標本は〈文化遺産〉と言ってもいいこと、その〈遺産〉を継承していくことの意義などについて、お話しました。
場所 アートのお寺 安国院 橘ギャラリー
🔊https://www.facebook.com/photo/?fbid=503199525553419&set=pcb.503199925553379
🔊https://www.facebook.com/share/p/5PHzeqwKaZoaK1jQ/
2024年7月27日「じゅん菜池を考える会」
「井上ひさしと国分ー『ドン松五郎の生活』を中心にー」根岸英之
日本を代表する作家・劇作家の井上ひさしさん(1934-2010)は、市川市国分(1967-1975)と北国分(1975-1987)に居を構え、
多くの小説・戯曲・エッセイなどを執筆しました。
そこには、中国分周辺を描かれた作品も多く、今読んでも、いろいろなメッセージを受け取ることができます。
今回は、人間のことばが理解できる犬が主人公の小説『ドン松五郎の生活』(1975)を採り上げて、皆さんで輪読してみましょう。
講演の様子は、『市川浦安よみうり』2024年8月3日号に掲載されました。
会場 市川市西部公民館(市川市中国分)
🔊https://www.facebook.com/share/xUReTeZZ2vkU2tyG/
🔊『市川よみうり』「市川文芸歳時記《114》中国分
街回遊展~井上ひさしさんが歩き描いたまち」2012年10月13日号
http://www.ichiyomi.co.jp/oriori/2012ori.html#9
画像 井上ひさし『ドン松五郎の生活』新潮社
2024年8月3日号「市川浦安よみうり」
「国府台・真間に住みつく”まちわらし”とは いちかわ市民ミュージカル 9月に公演」
2面には、〈市川学〉コーディネーターの立場からの私の取材コメントも取り上げてくださいました。
このなかで用いた”思い残し”ということばは、ミュージカルのなかでも使われていますが、宮沢賢治の作品をベースに、井上ひさしさんが、好まれて使ったことばでもあります。
宮沢賢治は「ざしきわらし」の童話も書いていますね。
このミュージカルには、宮沢賢治や井上ひさしさんなどの思想も、奥に込められています。
いちかわ市民ミュージカル

2024年10月12日「じゅん菜池を考える会」
「井上ひさしと国分ー『偽原始人』を中心にー」根岸英之
日本を代表する作家・劇作家の井上ひさしさん(1934-2010)は、市川市国分(1967-1975)と北国分(1975-1987)に居を構え、多くの小説・戯曲・エッセイなどを執筆しました。そこには、国分から国府台にかけて描かれた作品も多く、今読んでも、いろいろなメッセージを受け取ることができます。
今回採り上げる『偽原始人』(1976)朝日新聞社は、大人に反乱を起こす小学生たちが主人公の小説で、国分周辺の風景や環境問題、教育問題などが語られています。
井上さんの問題意識を一緒に考えてみましょう。
会場 市川市西部公民館(市川市中国分)
🔊https://www.facebook.com/share/xUReTeZZ2vkU2tyG/
2024年11月30日「日本口承文芸学会第86回研究例会」
「シンポジウム 大人が聞く「むかしばなし」―地域の中で「むかしばなし」はどのように伝えられていくのか―」
「市川民話の会の取り組みから」根岸英之
日本口承文芸学会研究例会で、市川民話の会の取り組みを元に、パネリストとして研究報告を行いました。
0.はじめに
1.市川民話の会会員へのアンケートから
2.「第47回市川の民話のつどい」来場者アンケートから
3.さまざまなメディアによる伝え方
4.市川民話の会における「むかしばなし」伝承の特色
5.「むかしばなし」の伝承論へ
これまで「伝承の語り手」と「新しい語り手」は、とかく二分法で論じられることが多かったのですが、同じ地平で論じていくことができるのではないか、といった点や、語り活動を「実践するアート」として捉えていく視点、などを提起しました。
2025年1月18日「じゅん菜池を考える会」
「井上ひさしと国分 第3弾ーエッセイを中心にー」根岸英之
日本を代表する作家・劇作家の井上ひさしさん(1934-2010)は、市川市国分(1967-1975)と北国分(1975-1987)に居を構え、多くの小説・戯曲・エッセイなどを執筆しました。そこには、国分から国府台にかけて描かれた作品も多く、今読んでも、いろいろなメッセージを受け取ることができます。
今回は、『家庭口論』(1974・中央公論社)、『聖母の道化師』(1981・中央公論社)などのエッセイに描かれた国分地区周辺のエピソードを読みながら、高度経済成長期の国分地区周辺の生活環境などについて振り返ってみたいと思います。
会場 市川市西部公民館(市川市中国分)